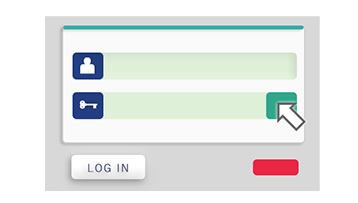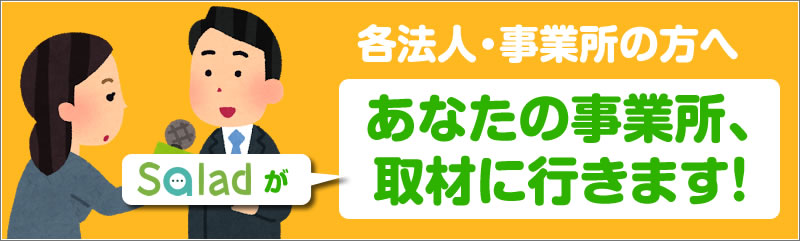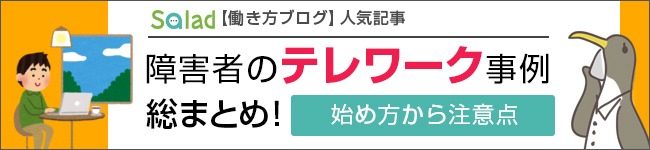なぜロボットみたいと言われるのか? それのどこが悪いのか
ロボットみたいと言われる理由と、言われて傷つくわけ
 あなたは職場や学校などでロボットみたいと言われた経験はありますか?
あなたは職場や学校などでロボットみたいと言われた経験はありますか?
直接でなくても、陰口や人づてに言われていたことを知る場合もあるかもしれません。
発達障害の特性を持っている人の場合は特に、周囲の人からそう言われたら傷つくことと思います。
発達障害にはADHD・ASDなど様々な分類があり、人とのコミュニケーションの取り方や興味の持ち方、感覚などが、 定型発達の(発達障害がない)人たちとは少し異なる場合があります。
例えば、会話のキャッチボールが苦手だったり、相手の表情や声のトーンを読み取ることが難しかったり、特定のことに深くのめり込んでしまったり、音や光に敏感だったりするかもしれません。
こうした特性が周囲の人から見ると「ロボットみたい」と捉えられてしまうことがあります。
あまりないとは思いますが、「ロボットみたい」という言葉が一部の能力の高さを表現しているケースもあるかもしれません。
正確で論理的な思考ができる、集中力が高い、私情や欲にまどわされずに公正な判断ができるなどの点を「人間にはできないようなことができる」という意味でロボットみたいと表現している場合です。
ただし、能力が高い反面、感情表現ややさしさ、人への気遣いなどの配慮には欠けるというニュアンスも含まれているために、見下した言い方になっていることには注意しましょう。
ほとんどの人はロボットみたいと言われていい気分はしません。
学校ならいじめにあたる発言かもしれません。
人を中傷し、陰口や悪口を言う人のほうが悪いです。
職場で個人の障害特性をからかうのは悪質なハラスメントと言えます。
ただ、言われた方の人は全く悪くないのですが、「ロボットみたいと言われたくない、そんなことを言われないように自分を変えたい」と思う気持ちもあると思います。
この記事ではロボットみたいと言われて傷ついた人、言われたくない人、言われた時に何をどう改善すればいいのか、どこが悪いのか悩む人へ、具体的な対策やコミュニケーションをスムーズに改善するテクニックについてご紹介します。
発達障害の私が「ロボットみたい」という言葉に落ち込み、向き合った結果得たもの

同じ経験をする人は多いが、どう反応するのかはあなた次第
自分がロボットみたいと言われたことを知ったとき、あなたはまずどう思うでしょうか?
きっと落ち込み、傷つくと思います。
私にも似た経験があります。
感情表現のぎこちなさ、周囲の人への配慮には欠けると思われていることに落ち込んだり、見下した言い方をされ、陰口を言われて笑いものにされたことに傷つくのはあなただけではありません。
ただ、それをどのように受け止め、「ロボットみたい」という言葉を投げつけてきた人とどう関わっていくかはあなた次第です。
積極的に何かするのではなく、いつか記憶が薄れてつらさが忘れられるときまで、トラウマ、心の傷としてそのまま放置するという選択肢ももちろんあります。
さまざまな選択があると思いますが、私がロボットみたいという言葉と向き合って考えたこと、その結果として得たものについてシェアします。
他者からの中傷に向き合ったプロセス
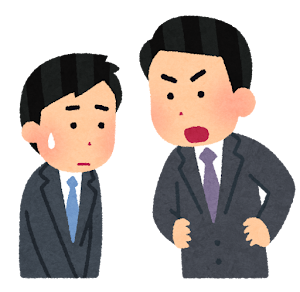
私の場合、ロボットみたいという言葉と向き合っときのた考えは、時系列順に二つの段階に分かれます。
まず第一段階として訪れた状態は「ステップ1:言葉を受け止め、心の傷と向き合い、悪口に負けない心のタフさを身に着けたいと思う」ことでした。
その次に訪れた段階は「ステップ2:自己肯定感を保ち、自分らしく働くためにできることを考える」ことでした。
順番に説明していきます。
ステップ1:言葉を受け止め、心の傷(トラウマ)と向き合い、悪口に負けない心のタフさを身に着ける

悪口・陰口や差別発言をどう受け止めるか、その人たちとどう関わっていくのか?
悪口や差別的な発言、中傷を受けて悲しみ、傷つくことはおかしいこと・悪いことではありません。
人として当然の反応です。
悪口や差別発言は言った方が悪いです。
悪口を言った上に「あれぐらいのことを根に持って…」「気にしすぎ」などと開き直って追い打ちをかけてくる人もいますが、悪口や差別発言は言った方が悪い、これに間違いはありません。
ただし、だからといって悪口を言った人を辞めさせて職場から追い出したり、差別やいじめがある職場・組織の雰囲気や人間関係を変えることが難しいのも事実です。
自分の思い通りに他人を動かしたり、組織・職場の慣習や体質を変えるのは非常に困難です。
できたとしても実現には多大な時間と労力、他の人の協力が必要になるでしょう。
一方、自分の行動は自分で選択できます。
善悪、良し悪しはいったん脇に置いておいて、自分の心も守るためにできることを考えたてアクションした方が、結果的に傷は早く癒せるのではないでしょうか。
悪口やいじめの蔓延する環境の悪い職場は無理に我慢したり変えようとしたりせず、程度や状況を見きわめて見切りをつけ、辞めて転職するというのも前向きで効率的な決断です。

もうダメかも…そんな時に思い出してほしい「トラウマ・PTSD」の話
はじめに – トラウマってなんだろう?
トラウマという言葉を最近よく耳にしますが実際にはどんなものか知っていますか?
トラウマとは一般的に、心に深く残るような、つらい出来事のことを指します。
例えば災害・事故・虐待・DV・いじめ・ハラスメントなど、命の危険を感じるような体験や、耐え難い苦痛を伴う体験がトラウマになることがあります。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)って何? トラウマとの違いは?
PTSDは命の危険を感じるような強烈な体験をした後に、心身に様々な症状が現れる障害です。
わかりやすく単純化して説明すると、つまりトラウマが原因となって起きるのがPTSDです。
米国精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアルであるDSM-5によるとPTSDは以下の特徴を持ちます。
[1]外傷的出来事:死の危険に直面したり、目撃したり、または親しい人にそのような出来事が起こった
ことを知るなど、トラウマとなる出来事を経験していること。
[2]侵入症状:外傷に関連する記憶、悪夢、またはフラッシュバック(過去のトラウマ体験が突然蘇る)などの反復的な再体験
外傷に関連する刺激に対する強い心理的または生理的反応
[3]持続的な回避:外傷に関連する思考、感情、または記憶を避けようとする
外傷を思い出させる場所、人、または状況を避けようとする
[4]否定的認知と気分の変化:外傷に関する否定的な信念や感情(例:自分を責める、世界は危険だなど)
喜びや幸福を感じにくい、または感情が乏しくなる
[5]覚醒と反応性の亢進:常に警戒している状態・集中力の低下・睡眠障害(不眠、悪夢など)・些細なことで怒りやすくなる
これらの症状が1ヶ月以上続き、日常生活に支障をきたす場合にPTSDと診断されます。
PTSDは誰にでも起こりうる心の病気です。
つらい症状が続く場合は一人で悩まず、専門機関に相談してください。
参考:PTSD|こころの情報サイト|厚生労働省
参考:心的外傷後ストレス障害 (PTSD) – 10. 心の健康問題 – MSDマニュアル家庭版
2. トラウマがもたらす影響、症状とは?
トラウマの影響は人それぞれですが、よくある症状をわかりやすく説明すると、
・フラッシュバック:辛い記憶が突然蘇り、苦しくなる
・回避:トラウマを思い出す場所や人を避ける
・感情の麻痺:感情が鈍くなり、喜怒哀楽を感じにくくなる
・不眠:寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりする
・イライラ:ちょっとしたことで怒りやすくなる
・集中力低下:何かに集中することが難しくなる
などがあります。
これらの症状が続くと日常生活に支障をきたし、仕事や人間関係にも悪い影響が出ることがあります。
3. トラウマを癒すための3つのセルフケア + 5つの専門的治療法
トラウマを癒すために自分でできる3つのセルフケアのアプローチと、代表的な5つの専門的治療法を紹介します。
セルフケア1:まずは「安心・安全」を確保する
トラウマを抱えている時は、心も体も緊張している状態が続いています。
まずは、心身ともにリラックスできる環境を作ることが大切です。
・睡眠時間を確保する
・バランスの取れた食事を摂る
・好きな音楽を聴く
・アロマテラピーを試す
・瞑想やヨガをする
など、自分に合ったリラックス方法を見つけ、実践してみましょう。
セルフケア2:「今ここ」に意識を向ける
トラウマ体験を思い出して辛くなった時は、今ここに意識を向けるようにしましょう。
過去の出来事に囚われず、今、自分はここにいるという感覚を取り戻すことで、不安や恐怖を和らげることができます。
・深呼吸をする
・五感を意識する(例えば、周りの音や匂いを感じてみる)
・軽い運動をする(身体感覚に意識をシフトする)
など、今に意識を向けるための具体的な行動をいくつか持っておくと良いでしょう。
セルフケア3:自分を大切にする
トラウマを抱えている時は自分を責めてしまう気持ちになりやすいかもしれません。
「私が悪いんだ」「もっとこうすれば良かった」と自分を責めるのではなく、「辛かったね」「よく頑張ったね」と自分を優しく労わることが大切です。
・好きなことをする
・自分にご褒美を与える
・誰かに話を聞いてもらう
など、自分を大切にするための行動を積極的に行いましょう。

代表的な5つの専門的治療法
1. 薬物療法
抗うつ薬や抗不安薬などを用いて症状を緩和します。
現在精神科や心療内科で治療を受けている人がトラウマについて主治医に相談する場合、まずこの薬物療法による対処から行うことになるケースが多いでしょう。
医師の指示に従い、適切な容量・用法を守って薬を服用することが大切です。
2. 持続エクスポージャー療法(PE)
トラウマ体験を徐々に思い出すことで、不安や恐怖を克服していく治療法です。
ただし、一人で無理にチャレンジすることは、パニックや悪化の可能性もあり、危険です。
安全な環境で専門家のサポートのもとで行うことが推奨されます。
3. 認知処理療法(CPT)
トラウマ体験に関する誤った考え方や解釈を修正する治療法です。
認知行動療法の一環として行われます。
4. 眼球運動脱感作療法(EMDR)
目を左右に動かしながらトラウマ体験を思い出すことで、感情的な苦痛を軽減する治療法です。
専門家のトレーニングを受けたセラピストが行います。
5. TSプロトコール
TSプロトコールはトラウマ治療の比較的新しい心理療法です。
トラウマ体験は、感情だけでなく、身体にも深く刻まれます。
そのためTSプロトコールでは、トラウマを解消するには身体感覚へのアプローチが不可欠だという考えに基づき、身体の動作を行うことでトラウマ記憶に関連する感情や思考を変化させ、PTSD症状を軽減すると考えられています。
TSプロトコールは新しい治療法であり、研究が進められている段階です。
効果や安全性については、今後の研究結果が注目されます。

5. 助けを求めることも大切
誰かに相談すること、助けを求めることは、あなた自信を守る勇気ある行動です。
病気は適切な治療を受けることで回復することができます。
トラウマの症状が改善しない場合は、専門家のサポートが必要となることもあります。
精神科医・臨床心理士・カウンセラーなどの信頼できる専門家に相談し、適切なアドバイスや治療を受けることを検討しましょう。
治療に取り組みながら日常生活を送る際には家族や友人、パートナーの理解があると、より心強く、安心感が感じられるでしょう。
自分の抱えている問題・状況 – 話すのが辛ければ「今、自分は職場の人間関係に悩んで、心身の症状が出て困っている」と伝えるだけでも構いません – について説明し、治療に取り組んでいることを話せば、きっと励まし、応援する気持ちをもって見守ってくれることと思います。
身近な人に話しにくい場合でも、電話相談・SNS相談などを利用して話すことで気持ちを軽くすることもできるかもしれません。
トラウマを抱えているあなたは、決して一人ではありません。
つらい時は無理せず、周りの人に頼ったり、専門家の力を借りることも考えてみましょう。
ステップ2:自己肯定感を保ち、自分らしく働くためにできること

前の段階では、現状を受け止めることと辛さを和らげるためのアプローチについて説明しました。
その先の段階として、今後同じ事を言われないようにする・言われた時に深く傷つかないようにするために自己肯定感を保ち、自分らしく働くためにできることについて紹介していきます。
私の取り組んだことは感情表現・コミュニケーションの改善のためのテクニックを学び実践することと、環境にアプローチする・専門家の力を借りてできることの二種類に分かれました。
順に説明していきます。
感情表現・コミュニケーションのぎこちなさを補うためのテクニック4つ
ロボットみたいと言われる大きな原因のひとつは感情表現やコミュニケーションのぎこちなさです。
ここではこのぎこちない感じを補い、コミュニケーションをスムーズに見せるためのテクニックをご紹介します。
テクニック1:事前に準備する
会議の議題や話す内容を事前に整理しておくことで、スムーズなコミュニケーションが可能です。
テクニック2:具体的に話す
「昨日言われたアレ、できましたが…」などと抽象的な表現ではなく「昨日、〇〇の資料を作成しました」のように、具体的に話すことで、相手に正確に伝わります。
テクニック3:視覚的な資料を活用する
図やグラフなど、視覚的な資料を使うことで、より分かりやすく伝えることができます。
テクニック4:フィードバックを求める
話の途中で、時々相手に「ここまででわからないことは何かありますか?」と確認することで、誤解を防ぐことができます。
コミュニケーションを円滑にするツールを使うテクニック3つ
コミュニケーション、特にビジネスコミュニケーションを円滑にするために便利なツールがあります。目的や状況に応じて、積極的に試してみましょう。

テクニック1:コミュニケーションアプリを使う
Slack、Teamsなどのコミュニケーションアプリを活用することで、手軽に内容が整理されたコミュニケーションを行うことができます。
コミュニケーションアプリを利用すると宛先、トピックなどをわかりやすく指定でき、受け手もリアクションがとりやすいというメリットがあります。
テクニック2:視覚的に情報を共有するオンラインツールを利用する
Googleドキュメントでテキストや表、スライドを共有したり、Canvaなどのオンラインツールでデザインや図を共有することで、より分かりやすく伝えることができます。
テクニック3:タスク・スケジュール管理ツールを利用する
Googleカレンダー、LINEなどの予定を管理するツールを活用することで、タスク管理やスケジュール管理を効率的に行うことができます。
共有のカレンダー上でイベントを作成してメンバーを招待し、詳細情報を共有したり、リマインダーを自動で送信したりできます。
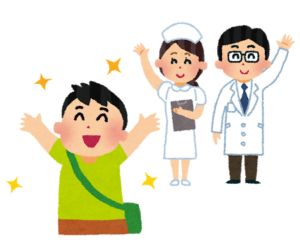
環境にアプローチする・専門家の力を借りてできること
環境調整
上司や同僚が障害に対する理解があり(コンプライアンス・社内での教育が行き届いている)、組織的にハラスメントの予防・対策がなされている職場で働くことで、差別的ないじめや悪口にあいにくくなり、また、あったとしても適切なサポートが受けられます。
我慢して悪口やいじめ、差別の蔓延する職場にとどまり続けると、心身の負担が大きくなります。
もし職場環境が悪いと気づいた場合は、程度や状況(改善が可能か、自分を守ることができそうか)を考慮して、無理そうならできるだけ早く見切りをつけ、辞めるというのも前向きで効率的な決断です。
自分のことだと「この職場はおかしいのではないか?」と冷静に判断することが難しくなることもあるかもしれません。
そのようなときは、外部の第三者に相談してみるのも参考になるでしょう。
主治医、電話相談の窓口や、地域の障害者就労支援機関の職員など、いろいろな人の意見を聞いてみましょう。
相談相手は家族や友人でも良いのですが、親しい人だと心配や気遣いの気持ちから「頑張って」「大丈夫だよ」と言われてしまうかもしれないので、冷静に判断できる第三者への相談をおすすめします。
専門家によるコミュニケーションスキルのトレーニング- SST
SSTとはSocial Skills Training(ソーシャル・スキルズ・トレーニング)の略称で「社会生活技能訓練(または生活技能訓練)」のことです。
考え方や思考のくせを見つけ改善する認知行動療法と社会学習理論をもとにした支援方法の一つで、さまざまな医療・教育機関で取り入れられています。
SSTの目的は主に精神障害や発達障害を持つ人が社会生活の中で対人関係を良好に維持する機能を身につけることですが、発達障害の有無に限らず、あらゆる「対人関係に困難を感じるケース」に適応できる内容となっています。
自分の障害に関する知識を深めることも、自分を知り、有用性のある対処法を身に着ける手段になります。
SSTは職場・学校でのコミュニケーションに困った際に効果的なトレーニングと言えます。
参考:精神科デイケア│小石川東京病院
参考:SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは|統合失調症・精神科救急・急性期治療の吉祥寺病院(東京調布、吉祥寺、三鷹の精神科)
仕事・働き方に悩んでいたら。『Salad』が強みを活かす就職のサポートをします
まとめ
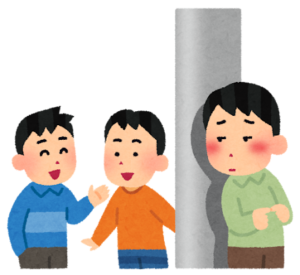
他人や環境を変えるのは難しいが、自分でアクションし、何ができるか考えることはできる
職場や学校など、いろいろな人がいる環境では、どんな人でも悪口・陰口や差別的な言葉を言われてしまう可能性はあります。
自分の人間性・性格や障害特性のせいと思って落ち込むかもしれませんが、ネガティブな言葉で傷つけられることはどんな人でも…障害のあるなしにかかわらず起きる事態です。
悪口や差別発言は言った方が悪いですが、だからといって悪口を言った人を職場から追い出したり、差別やいじめがある職場の雰囲気や人間関係を変えることは現実には難しいです。
事態をどのように受け止め、どうアクションするか、周囲の人とどう関わっていくかはあなた次第です。
悪口を言われたくない、言われないように環境を変えたい、自分を変えたいと思う気持ちがあるとき、そのために何ができるのか考えてみることで一歩前進となるのではないでしょうか。
障害者雇用で職場環境がミスマッチだと考えている人、自分らしく強みを生かして働きたい方は一度『Salad(サラダ)』にご相談ください。
自分の得意としていることや好きなことを『強み』として働き続けるための様々なサポートをしております。
IT・Webに強い障害者雇用の非公開求人はこちらからご覧いただけます。
【サラダ編集部公式SNS】X・Instagram参考:職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要(令和5年度厚生労働省委託事業)|厚生労働省 (PDF版)
参考:「相談サポート通信 相談者実態調査」「トラブルの多い職場の傾向」に関するアンケート調査| アスクプロ株式会社 AskPro, Inc.のプレスリリース









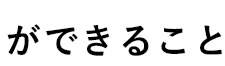
 カスタマイズ就業って?
カスタマイズ就業って?

 ノウドー求人情報画面
ノウドー求人情報画面