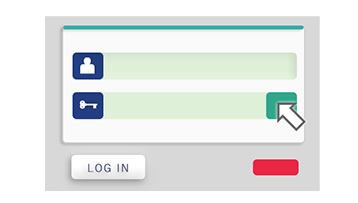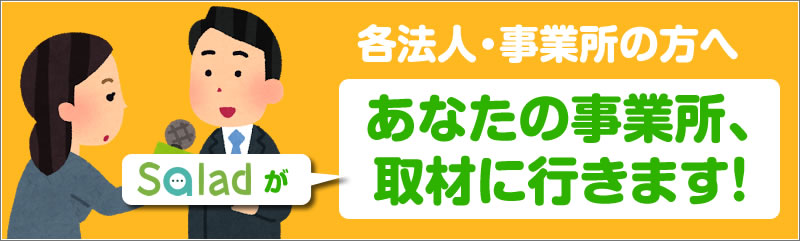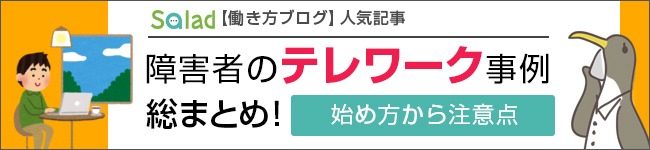自傷行為の当事者を追い詰める、誤解と偏見
 周囲の人の理解がない…偏見と誤解に苦しむ自傷当事者
周囲の人の理解がない…偏見と誤解に苦しむ自傷当事者
「自分で『死ぬ』と言う人は死なない」といった、昔から言われてきた自傷行為に対する通説が、実際は間違っていることが分かってきています。
例えば『「死ぬ」と言う人は死なない』とか、『自傷は甘えの強い「かまってちゃん」がする、アピール行為』といった考えは実際には間違いであることが医学的な調査により明らかにされてきました。
このような誤った偏見から発生する心ない言葉は当事者を傷つけ、言われた時だけでなくその後も長期間にわたって苦しめて信頼関係を損ない、当事者を孤立させて追い詰める可能性が高く、有害で危険です。
現在、治療の現場では自傷行為のリスクを正しく認識し、より適切な対応ができるよう試行されてきています。
現在蔓延している誤った有害な偏見について訂正し、最新の治療の現場で行われている対応を紹介します。
自傷行為に関する4つの誤解

誤解その1:「死ぬ」と言う人は死なない?
自傷行為を繰り返す人を見て「死にたいと言っているのに、結局は死なない」と安易に判断してしまうことがあります。
しかし、自傷行為をする人は自殺のリスクが低い、危険ではないという考えは大きな誤解です。
精神科通院中の女性自傷患者のうち、18.9%が1年以内に医療機関で治療が必要なほど重篤な過量服薬を行っており、22.4%が3年以内にきわめて致死性の高い手段・方法で自殺企図におよんでいることが明らかにされています。
また、10代のときに自傷行為を行った若者が10年後に自殺既遂で死亡している確率は400~700倍に高まるという研究結果もあります。
自殺や致死性の高い自傷行為に移行する前に適切な介入を行い、治療につなげることが重要です。
誤解その2:自傷行為は甘え?
恵まれた環境で育った、自己愛や甘えが強い人が自傷行為を行うというのは誤りです。
実際には虐待や不適切な養育環境が自傷行為と関係していることが分かってきました。
習慣的な自傷がある患者の約6割に幼少期の身体的・性的虐待が認められるという報告があります。
また、女性自傷患者の61.8%に身体的虐待が、41.2%に性的虐待が認められたという調査結果もあります。
ただし、忘れてはならない注意点は虐待がない環境で育った人でも自傷行為を行うケースがあるということです。
約6割に幼少期の身体的・性的虐待の経験があったとしても、残りの4割の患者には虐待の経験はありません。
早計に自傷行為=虐待の結果と決めつけないよう、注意が必要です。
誤解その3:自傷行為をする人はパーソナリティ障害?
自傷行為がパーソナリティ障害と結びつけて考えられてきた時期もありましたが、今は必ずしもそうでないと考えられています。
パーソナリティ障害の症状として、自己破壊的で衝動的な行動、自傷行為が起こる場合もありますが、現在では自傷行為がある=(イコール)パーソナリティ障害ではなく、さまざまな要因があると考えられています。
自傷行為に関する3つの意外な事実

[1] OD(オーバードーズ)は自傷に含まれる?
過量服薬(OD・オーバードーズ)はリストカットなど狭義の自傷行為よりより自殺に近い行動と考えられています。
精神科で治療のために処方された薬や風邪薬などの市販薬を過量服薬するケースも多いので、薬の処方や管理に注意が必要になる場合もあります。
参考:濫用等のおそれのある医薬品について|厚生労働省
参考:一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (一般の方へ)|厚生労働省
[2] 摂食障害・薬物乱用など、他の危険行為との関わり
一般の中学生・高校生において自傷行為の経験は、飲酒・喫煙の習慣や薬物乱用のリスクと関係があり、拒食や過食といった摂食障害や、性的な危険行動(援助交際などの不特定多数との性交渉、避妊しない性交渉)とも関連します。
薬物乱用、摂食障害、性的な危険行動も、健康や生命に大きな害を及ぼすリスクの高い危険な行動ですので、あわせて注意と対処が必要です。
[3] タトゥーなどの身体改造と自傷行為の違い
リストカットなどの自傷行為が、過度なピアスやタトゥーなどの身体改造行為に移行し、その間は自傷行為が止まる場合もあります。
この場合の自傷行為の代わりとしての身体改造行為は、文化的な探求としての身体改造行為や、反社会的な集団における刺青などとはまた異なります。
ただし、自傷行為の経験者が過度なピアスやタトゥーなどをすることが多い傾向はありますが、順序としては、まず先に自傷行為があって、その後にピアスやタトゥーなどに移るので、医療の現場では自傷行為への適切な対応が優先されます。
参考:石井光太が語る「路地裏に立つ女性たち」 – クローズアップ現代 – NHK
参考:身体改造 – Wikipedia【※リンク先に閲覧注意の写真あり】
自傷行為に関する間違った対応3つ

[1] 罰を与えれば自傷行為をやめされられる?
罰を与えればやめると考え、私的に痛みや経済的な制裁を与える人もいますが、罰を与えることは自傷行為の治療に対する効果はありません。
麻酔なしで治療(縫合など)しようとする医師、治療費用を全額負担させようとする病院職員が存在したというケースを見聞きしたことがありますが、精神疾患が理由の自傷行為への治療は保険の適用が可能です。
罰として故意に痛みを感じさせるために無麻酔での治療を行おうとしたり、医療費を全額自己負担で請求する行為は、その人個人(または所属する組織)によるリンチ(私刑)です。
もしそのような対応をされそうになったら、病院のハラスメント通報窓口、医療に関する相談窓口(電話など)や、全国の医療安全支援センターなどに相談しましょう。
自傷行為が習慣的になりアディクションとなっている場合は特に、依存症と同様、罰すること、禁止すること、やめると誓わせることは無意味です。
自分の意志で自傷行為をやめるのが困難な患者に対して、自分の精神論を語って説教したり、根性論で「やめろ」というのは、治療に効果はなく、むしろ患者との信頼関係を損なう、治療(患者)にとって有害な行為です。
参考:港区ホームページ/国民健康保険被保険者証が使用できないものについて知りたい。
参考:依存症対策~やめたくてもやめられない方々へ~ ご家族の皆様へ 横浜市
参考:ドクターハラスメントとは? 被害に遭った場合の相談窓口を紹介 | 弁護士JP
[2] 自傷行為はアピールだから、無視すればしなくなる?
かまってほしくて自傷行為するのだから、無視していればおさまるという考えも広まっています。
そもそも自傷行為が他者へのアピールであるという前提が誤っているので、この考えは正しくありません。
自傷行為を止めさせたいときには、無視よりも適切な介入、治療のほうが効果があります。
ただし、過剰に反応しすぎて、患者に振り回される状況では治療が効率的に進められません。
医療機関では最初に守るべき約束(予約した診察時間外は対応しない、自傷したら記録を付ける、適切な治療をするなどの決め事をして、約束を破ったら対応をしないという約束)を決めたうえで治療する方針がとられています。
[3] 精神科の病棟に入院させれば解決する?
緊急時に短期入院することで監視し、自傷行為を防いで安全性を確保することが効果的な場合もあります。
一般的に家族やパートナーが家事や仕事をしながら患者をずっと見守ることは難しいので、そのような周囲の人の負担を減らすことができるのは有意義です。
ただ、入院して刃物などを取り上げ、24時間監視しさえすれば、問題が解決するとは限りません。
退院して監視の目がなくなれば自傷行為が再発してしまうようでは、根本的な解決にはなっていないからです。
「精神科病院への入院が自殺を減らすというエビデンスはなく、自殺は、他のいかなる施設よりも、精神科病棟と刑務所で起きている」という見解もあります。
自分の意思に反して不本意に入院させられてしまったという経験になって、患者と周囲の人との関係が悪化したり、入院する環境に依存してしまったりという、入院自体の悪影響について考えたうえで、入院治療を行うかどうか慎重に検討する必要があります。
仕事・働き方に悩んでいたら。『Salad』が強みを活かす職のサポートをします
まとめ

自傷行為の現状と今後
10代の若者の10人に1人が自傷行為の経験があると言われていて、これは決して他人事として無視することができない多さです。
ただし、この10人に1人という数字は教員などが発見できた”氷山の一角”のケースにすぎず、実際の自傷経験者-潜在的な数はもっと多いはずです。
このように多くの人が苦しむ問題にもかかわらず、社会全体に自傷行為に対する誤った知識が蔓延していて、当事者やサポートする周囲の人を苦しめている現状があります。
現在は再発のリスクに対する支援の取り組みや、自傷行為の傷跡を目立たなくするための治療法の研究も行われています。
多くの人が持っている自傷行為に対する誤解や偏見が修正され、新しい知識を得て理解を深め、社会全体が当事者をサポートする体制が整うことが、より効果がある対策となるでしょう。
参考:リストカットは「生きる」ため。自傷行為の正しい意味を専門家に聞いた | 日本財団ジャーナル
参考:自傷によるきずあとの隠し方 | 日本自傷リストカット支援協会 JSWSA







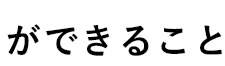
 カスタマイズ就業って?
カスタマイズ就業って?

 ノウドー求人情報画面
ノウドー求人情報画面