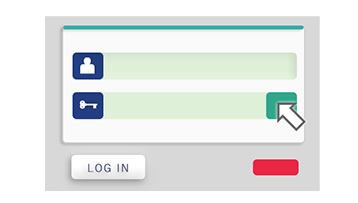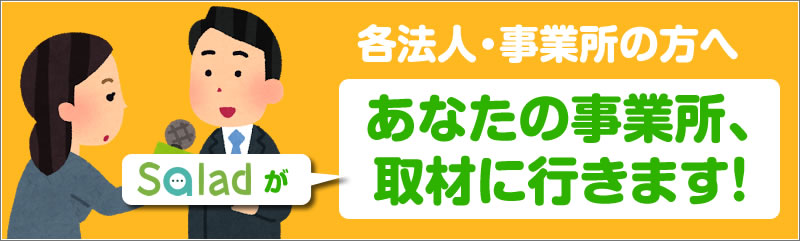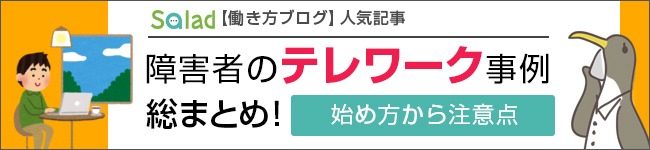こんにちは! ASDで病院に行くと体調が悪くなる、サラダ編集部の「やまね」です。
今日は、私が最近利用したオンライン診療についてお話したいと思います。
ファストドクターを選んだ理由と、通院がつらいわけ

なぜオンライン診療を選んだのか?
薬が必要になったり、休んでも自然回復しない体調不良になることは誰にでもあると思います。
そんな時は病院には行かなければなりませんが…みなさんは病院に行くと体調が悪くなるということはありませんか?
理由はわかりませんが、私は病院に行くと体調が悪くなるのです。
平日は仕事をしていますから、大抵夕方か土日に通院しているのですが、病院に行った日の夜や翌日は必ず体調が悪くなります。
土曜日に通院したら、日曜日は体調不良で丸一日つぶれてしまいます…。
通院の予定が近づくと、それだけで気が重く感じ、大きなストレスでした。
特に遠方の病院や待ち時間が長い病院への通院はなおさら辛く感じます。
ファストドクターを知ったきっかけ
そんな時に知ったのがファストドクターのオンライン診療です。
Instagramのストーリーで、フォローしている発達障害のお子さんを持つママさんが紹介しているのを見てファストドクターを知りました。
体調の悪いお子さんを病院に連れていくのは大変ですよね。
毎日の家事と仕事も忙しい、子どもたちは保育園ではやった風邪や病気がすぐうつってしまう、他にまだ小さい下のきょうだいもいる、熱があると感染症対策で通常の内科や小児科は受診を受け付けてくれない…保護者はどんなに大変だろうか…と思います。
そんなママさんはお子さんの体調不良時にファストドクター(小児科)を利用している様子。
「病院に行かなくてよい」という発想がなかった私にとって、オンライン診療は目からウロコでした。
ファストドクターを実際に使ってみた感想
ファストドクターを使ってみた感想
実際に使ってみて、まず感じたのは待ち時間のストレスが減るという点でした。
病院のように出先で長時間待つ必要がないので、身体的・精神的な負担が大幅に軽減されました。
待ち時間の目安も表示されるので、診察後の予定や見通しが立てやすいのも安心しますし、助かります。
また、いつも病院の待合室で風邪や感染症がうつるのではないかと不安になるのですが、そもそも外に出ずに診察が終わるなら、その不安も解消されます。
また、プライバシーを守って診察を受けられるのも良かったです。
中には、待合室まで診察室で話している内容が筒抜け・丸聞こえの病院もありますよね…。
自宅でのオンライン診療では、周りの目を気にせず、自分の症状について落ち着いて説明することができました。
ビデオ通話で診察してくれる医師の姿を見て会話できるので、対面での診察と変わらない安心感がありました。

ファストドクターのアレルギー科で花粉症の薬をもらってみた
今回はちょうど1月末ごろで、花粉の飛散がニュースで報じられた時期で、くしゃみや目のかゆみが気になってきたので花粉症の薬が欲しくて受診することにしました。
私が見たときにはファストドクターのトップページに花粉症外来専用ページのバナーが表示されていたので選択し、オンライン診察申し込みのボタンをクリックして申し込みを行いました。
おくすり手帳の履歴を確認して、以前にアレルギー科で処方してもらっていたアレルギーの薬(内服薬と目薬)を伝えると同じものを処方してもらえました。
受診後、受け取り場所に指定した薬局から薬の用意ができた旨の連絡がありました(※薬局により、対応が異なる可能性があります)。
その後、手があいた時間に薬局に行き、薬を受け取って薬の料金を支払いました。
ファストドクターのオンライン診療の手順
ファストドクターの利用方法は、スマートフォンに慣れている人なら難しくはありません。
スマートフォンに慣れていなくて、SMSが何かわからない・カメラ(オンラインのビデオ通話)が使えないというレベルの人だと、少し難しいかもしれません。
参考:iPhoneでメッセージを設定する – Apple サポート (日本)
参考:電話番号のみでやり取りできる SMS とは? 概要や使い方、他のサービスとの違いを解説|Android
ただ、申し込み後確認の電話がかかってきて、担当者が「使い方などで何かわからないことはありませんか?」と聞いてくれたので、通話で説明を聞いてやり方をある程度は教わることはできると思います。
支払いはクレジットカードかNP後払い(コンビニ・郵便局・銀行で後払い)です。
診察の流れを順に追って説明します。
[STEP.1] スマホやパソコンで申し込みをする
ファストドクターの公式サイトから申し込みができます。
受診はスマホのブラウザ(safari、Chromeなど)と電話・SMS機能だけですべて簡潔するので、ファストドクターのアプリのインストールは必須ではありません。
[STEP.2] 保険証と支払い方法の登録をする
マイページで保険証と支払い方法を登録します。
スマートフォンで保険証の写真を撮影してアップロードし、支払い方法を選択します。
[STEP.3] ビデオ通話テスト
ビデオ通話テスト専用のページが設けられているので通話テストを行い、通話が可能な環境があることを確認します。
SMSと通話アプリでファストドクターから連絡が来ますので、スマートフォンの設定で連絡先に登録されていない相手からの着信を通知しない設定にしている人は、診察以来前にあらかじめ解除しておくとスムーズです。
参考:iPhoneで望まない相手からの着信を拒否する/避ける – Apple サポート (日本)
参考:携帯電話の電話帳に登録していない相手からの電話を拒否したい | よくあるご質問(FAQ) | NTTドコモ
[STEP.4] ビデオ通話開始、医師の問診
予約した時間が近づくとSMSで連絡が来て、マイページの通話開始ボタンがクリックできるようになります。
ビデオ通話で診察を受け、症状や病歴について医師に説明します。
以前処方された薬が欲しい人は、おくすり手帳など薬の種類や処方の履歴がわかるものを用意しておくとスムーズです。
[STEP.5] 処方箋の発行
必要に応じて、医師が処方箋を発行します。
ファストドクターのシステムにより、処方箋が指定した薬局に送信されます。
[STEP.6] 薬局での受け取り
処方箋は薬局での受け取りを選択した場合、指定した薬局に送られ、その薬局の薬剤師が薬を用意します。
私の場合は受診後、受け取り場所に指定した薬局から電話で薬の用意ができた旨の連絡がありました(※薬局により、対応が異なる可能性があります)。
薬の用意ができたら薬局で薬を受け取り、薬の代金を支払います。
薬局での受け取りの他に、薬を宅配してくれるサービスも選択できます(配送料金などがかかります)。

[STEP.7] 支払い
診察料はクレジットカードで支払いが可能です。
SMSで利用後5日以内に料金の連絡が来ます。
診察後、マイページで領収書・診療明細書がダウンロード可能(スマートフォンでも可)です。
私の受信時は受診から一か月後まで領収書・診療明細書がダウンロード可能と表示されていました。
診断書・診療情報提供書の発行を希望する場合は、発行依頼フォームから申し込みが可能です。
ファストドクターを利用するメリット
ファストドクターを利用して感じた利用のメリットについて説明します。

[メリットその1] 自宅で完結し、移動や待ち時間の負担が減る
通院の手間が省け、時間や移動の負担を減らすことができます。
また、病院で待つ際のストレスから解放され、他者との接触がないので感染症のリスクも減らせます。
たとえば下記のような場合にもオンラインでの受診が可能です。
・感染症(新型コロナ、インフルエンザなど)、発熱時、体調不良時の診察
・子ども、高齢者の診察
・遠隔地居住者や交通弱者の診察
・引っ越したばかりや旅行先で近所の病院がわからないとき
また、受診にはファストドクターのアプリが必須ではないのも良かったです。

[メリットその2] 自宅で診察できるためプライバシーを守れる
私が病院でイヤだな…と思うことの一つに、待合室まで診察室で話している内容が聞こえてしまうことがあります。
診察内容までは聞こえなくても、待合室で名前を呼ばれる場合もありますし、病院で知り合いに合ってしまう場合もありますよね。
その点、自宅でのオンライン診療なら人に知られず、プライバシーを守って診察を受けられるので安心して受診できました。

[メリットその3] オンライン診療では他者との接触がないので感染症のリスクが減らせる
病院には風邪や感染症の患者も来院するので、病院や薬局でうつるのではないかと不安になってしまうのですが、オンライン診療なら他の患者との接触の機会はなくなります。
気持ち的な問題かもしれませんが、この安心感は私にとっては重要です。

[メリットその4] 24時間対応で急な体調不良でも安心
私は車を持っていないので、急な体調不良時には救急車かタクシーしかないことが不安だったのですが、夜間・休日もオンライン診療の対応を受け付けてもらえると思うと安心です。
トリアージ(患者の重症度に基づいて治療の優先度を決定すること)を考えたとき、緊急搬送が必要な患者が最優先で救急車・救急外来などを利用することが望ましいと思い、自家用車などの交通手段を持っていない人が緊急・早期の受診が必要なのに受診をためらってしまう場合もあると思います。
鉄道などの交通機関の充実している大都市に住んでいる人は車を持っていない・自動車免許を持っていない(免許を返納した)人も多いと思うので、そのような場合も医療にアクセスしやすくなります。
ファストドクターを利用するときの注意点

時間外料金がかかる
通常の対面診療(病院での受診)もそうですが、時間によって診察料金が変化します。
受診する時間の料金を確認したうえで利用しましょう。
参考:時間外・休日・深夜の加算とは?初診・再診の場合ごとに解説 | メディコム | ウィーメックス株式会社(旧PHC株式会社)
参考:オンライン診療で時間外加算はどうなる?算定要件や必要な届出 | 株式会社インテグリティ・ヘルスケア
システム利用料金や薬の手配料がかかる
診療費以外に、システム利用料(330円)、また、薬の受け取りで配送を選択した場合は薬の手配料が追加でかかります。
JR東日本の初乗り料金が150円ですので、病院までの往復の交通費と比較して考えたらシステム利用料の方が安くなるケースも多いのではないでしょうか?
(※システム利用料、運賃の情報は2025年1月現在の情報です)
仕事・働き方に悩んでいたら。『Salad』が強みを活かす就職のサポートをします
まとめ
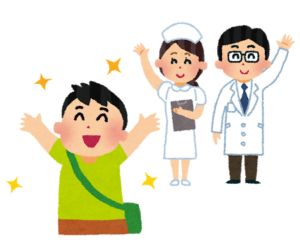
オンライン診療はまだ新しいサービスですが、今後ますます普及していくと思います。
感染症や体調不良時の診察、子ども、高齢者、遠隔地居住者や交通弱者などの受診の負担を減らすだけでなく、私のような病院が苦手な人にとっても便利なサービスですし、医師や病院スタッフ、薬局スタッフの手間や負担を減らすシステムとしても有用性が高いのではないでしょうか。
病院へ行くのがたいへん…忙しくて病院に行く余裕がない…という方も一度試してみてはいかがでしょうか。
この記事がオンライン診療サービスを選ぶ方の参考になれば幸いです。
参考:ファストドクター
実際に病院を受診する必要が出てくる場合もあります。
※また、薬の種類によっては処方できないものもあります。







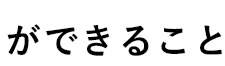
 カスタマイズ就業って?
カスタマイズ就業って?

 ノウドー求人情報画面
ノウドー求人情報画面