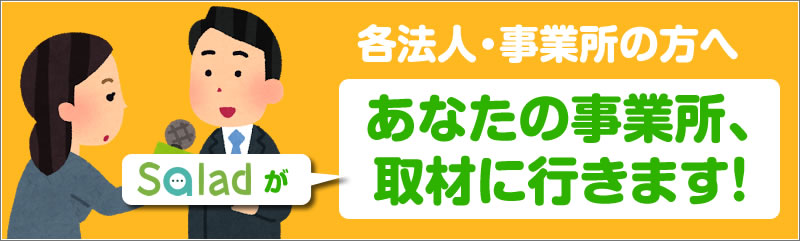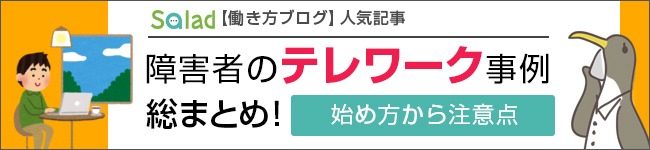音は聞こえるのに、言葉が聞き取れない…APD(聴覚情報処理障害)/LiD(聞き取り困難症)

難聴・聴覚障害とは違う、聞き取りの問題
みなさんは職場の人や友人との会話中、こんな風に思ったことはありませんか?
「あれ? 今、何て言った?」
「電話で相手の名前がどうしても聞き取れない…どうしよう、もう一度聞きなおしたら、相手は気分を悪くするかな…」
「音は聞こえるし、聴力検査でも問題ないんだけど…」
実はこのような問題で悩んでいるのはあなただけではありません。
APD(聴覚情報処理障害)という言葉をご存知でしょうか?
これは音が聞こえているのに、言葉として理解するのが難しい状態を指します。
LiD(聞き取り困難症)と言われることもあります。

APDとは?
APDは脳が音を処理する際に問題が生じ、言葉の意味を理解するのが困難になる状態です。
単に聞き間違いが多い、不注意ではなく、脳の働きに原因があると考えられています。
APDと他の病気との関係性
APDの直接的な原因となる疾患は、現時点では特定されていません。
多くの場合、脳の機能的な問題が原因と考えられており、遺伝的な要因や、脳の成長過程における異常などが関与している可能性が指摘されています。
APDと関連性の高い状態
APDは、必ずしも単独で起こるわけではなく、他の状態と併存することが多いです。
以下にAPDと関連性の高い状態を整理します。
発達障害
APDは発達障害(ASD、ADHD、LDなど)と併発することが多くみられます。
そしてそれぞれの特性が聞き取りや言語理解に影響を及ぼします。
たとえばASDの人に多く見られる聴覚過敏の状態、ADHDの特性としての集中力の欠如や衝動性、LD(学習障害)の特性として言語の理解や処理の困難などが、より聞き取りと理解を困難にすると考えられています。
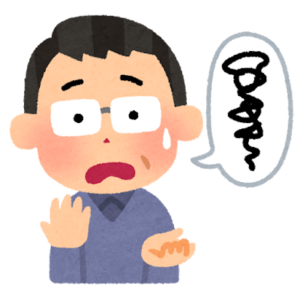 脳の損傷による高次脳機能障害
脳の損傷による高次脳機能障害
脳に損傷を受けた場合、言葉の聞き取りが困難になる症状が現れることがあります。
脳が損傷する主な原因としては脳梗塞・脳出血などの脳血管障害が代表的ですが、事故や怪我による脳外傷も脳の損傷の原因となります。
言葉は聞こえているのにその内容を理解できない、また、聞いたことを頭に留めることが困難な場合があります。
人によって症状の程度は異なり、言葉が全く理解できない人もいれば、短い会話は理解できるが、長い話を理解することは難しい人もいます。
参考:高次脳機能障害 障害特性|ハートシティ東京
参考:高次脳機能障害とは | 高次脳機能障害支援 | 千葉県千葉リハビリテーションセンター
その他の疾患、ストレスとAPDの関係性
APDの直接的な原因となる疾患は特定されていませんが、うつ病や適応障害、統合失調症など一部の精神疾患の症状ががAPDと併発して、コミュニケーションの困難さやストレス・負担が増し、症状が悪化するケースがあります。
また、APDの症状は脳の機能的な問題だけでなく、心の状態も大きく影響します。
特に不安やストレスは注意力を散漫にし、聞き取りに必要な集中力を低下させるため、言葉の意味を正確に理解することが難しくなるのです。
APD/LiDで困ること
APDにより、日常生活で様々な困りごとが生じます。
APDは、単なる「聞き取りにくい」という問題ではなく、脳が音を処理する際に困難が生じ、日常会話の理解や特定の音の聞き分けが難しい状態を指します。
具体的には下記のような問題が多いです。
・会話が聞き取りにくい
特に、複数人が同時に話している状況や、背景音が大きい場所では、何を言っているのか理解するのが難しい。
・集中力が続かない
周囲の音に気を取られてしまい、仕事や勉強に集中できない。
・コミュニケーションが苦手
会話の中で聞き返すことが多く、相手を不快にさせてしまうことがある。
APD/LiDの人のための日常生活・コミュニケーションの工夫
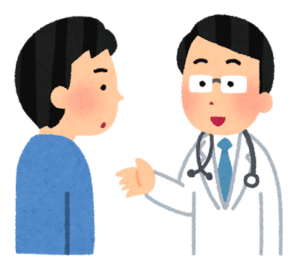
APD/LiDの人はどうすればいいの?
まずは耳鼻咽喉科で受診する
では、自分がAPDかもしれないと思ったとき、まずはどうすればいいのでしょうか?
聴覚情報処理障害(APD)であると診断されるには、聴力に異常がないことが前提となります。
他の病気が原因で聞こえの問題が起きている可能性もあるため、まずは耳鼻咽喉科で受診しましょう。
難聴と症状が似ているので、耳鼻科で聴力検査をしてもらい、耳の異常がないか確認しましょう。
[APD/LiD] 何が原因で、日常生活でどう対策すればいいの?
APDの原因や治療法はまだはっきりわかっていないため、症状を軽減し、より快適な生活を送ることができるように日常生活の中で工夫や対策を行っていくことが主な対処となります。
対策として、以下のような方法が考えられます。
・音を大きく、聞こえやすくする道具を使う
補聴器や補聴援助システムなど、聴覚補助機器を使うことで、聞き取りやすさを改善できます。
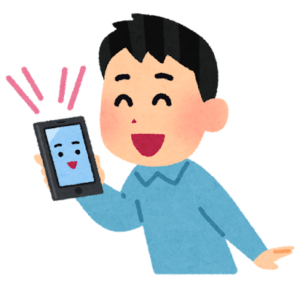
・字幕を利用する、録音する
動画の視聴時には字幕の機能をオンにしたり、会話を聞き取るときにはスマートフォンの音声入力機能、音声文字変換アプリを利用して音声を文字に変換して読むことで、聞き取りにくくても内容を理解しやすくなります。
また、ボイスレコーダーやスマートフォンの音声メモを利用することで、聞き取れなかった部分を再生して聞きなおすこともできます。
参考:iPhoneでテキストを音声入力する – Apple サポート (日本)
参考:UDトーク | コミュニケーション支援・会話の見える化アプリ
・道具で雑音を防ぐ
耳栓、ノイズキャンセリングイヤホン、イヤーマフなどを利用して、雑音をカットし、会話を聞き取りやすくする方法です。
環境や症状によってどれが適しているかは異なるので、いろいろ試して自分に合った・負担の少ない方法を探すことで、日常的に対策をしやすくなります。
・環境調整
静かな場所で作業をする、騒音源から離れるなど、周囲の環境を整えることで、聞き取りやすさを向上させることができます。
また、音声ではなくメールやチャットなどでの連絡がメインの仕事、テレワーク(在宅勤務)の仕事にに転職するなど、職場や働き方を変える方法もあります。
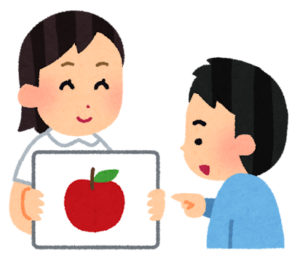
・トレーニング
外国語のリスニング学習や、知らない歌も繰り返し聞くことで歌詞を聞き取れるようになる要領で、トレーニングにより、聞いて理解する力を伸ばせる可能性があります。
・聞き取りのトレーニング
繰り返し聞き、耳からの情報を理解する力をつけるトレーニングを行います。
・書き取り(ディクテーション)
聞いた音声を文字に起こしたり、書いたものを見ながら音声を聞いたりします。
・聞くことに集中するトレーニング
好きな音楽や物語の朗読などを聞き取れるように注意しながら聴きます。
集中して聞く訓練をすることで、聞き取る力を高めることが目的です。
・語彙力+文脈から推測する力をつける
語彙が多いほど、前後の会話の内容や状況から言葉を推測しやすくなります。
読書やラジオ・ポッドキャスト・オーディオブックなどを聞き、さまざまな文章表現を知ることで、文脈から意味を推測する力も付きます。
これらのトレーニングを継続的に行うことで、少しずつ聴覚処理能力が向上し、日常生活の質が改善される可能性があります。
【注意】
ストレスになるような無理なトレーニングは避けましょう。
上記のトレーニング方法は、あくまで一般的な例です。APDの治療は、個人の状態や症状によって異なります。
必要に応じて、聴覚士や言語聴覚士、精神科医など、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
まとめ

初めてAPD/LiDを知り、自分はAPDではないか? と思ったとき、多くの人は戸惑い、不安を感じると思います。
ただ、なぜ自分だけが聞き取りにくいのかという悩みが解決し、自分の不注意ややる気のなさと思っていた「言葉の聞き取りの困難」の原因がわかったことで、必要以上に自分を責めなくて良いと感じ、安心する人もいるかもしれません。
これまでできて当たり前と思っていたことができず、自己肯定感が揺らぐこともあるでしょう。
しかし、自分の状況について知り、対策を行うことは、現状の困難を打開するための第一歩となります。
APDは、決してあなた一人だけの問題ではありません。
多くの人が同じような悩みを抱え、日々、生活と向き合っています。
自分の症状を理解し、周囲に伝えることで、より適切なサポートを得ることができます。
また、治療法は確立されていませんが、様々なアプローチを試すことで、日常生活の質を向上させることは可能です。
聴覚補助機器の活用や、コミュニケーションの工夫など、自分に合った方法を見つけることが大切です。
SNSなどで同じようにAPDと向き合っている人たちとつながり、情報交換をすることも、QOLの向上に役立つかもしれません。
APDの症状で職場環境を変え、障害者雇用で在宅勤務(テレワーク)の仕事に転職したいと考えている人、自分らしく強みを生かして働きたい人は一度『Salad(サラダ)』にご相談ください。
自分の得意としていることや好きなことを『強み』として働き続けるための様々なサポートをしております。
IT・Webに強い障害者雇用の非公開求人はこちらからご覧いただけます。
【サラダ編集部公式SNS】X・Instagram